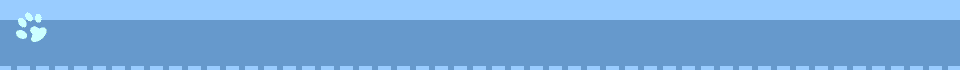電奇梵唄会奉納ソワカちゃん雑文祭 参加作品
私はかつて、初恋の相手と駆け落ちしたことがある。故郷に伝わる熊祭りの夜、部落の掟を破り二人で手を取り合い、この東京へやって来た。慎ましくも幸せな二人暮しが始まったが、残念ながら長くは続かなかった。ある日、私がバイトをしていたコンビニで、彼が他の客とトラブルを起こしたらしい。丁度私が休みの日だったので事情はよく分からなかったが、その日以来彼は塞ぎこみ、毎夜独りで悶え苦しむようになった。そして数日後、「フォーク並びを徹底してほしい」と記された一片の書置きを残して、彼は私の前から消えた。私が抱いたのは理不尽な仕打ちへの怒りではなく、寄る辺を失った喪失感だった。半分欠けた球体が回転運動を停止するように、彼の消えた日から私は生気まで失った。あの少年と出会うまでは。
「奇麗な眼をしておるな」
通りすがりに声を掛けてきたその少年は、少し古風な言い回しを好んだ。そこは西日暮里の駅前に広がるちょっとした商店街。低気圧の影響か、道行く人が皆少し眠たげな眼差しをしている、そんな日だった。少年にとっては気軽なナンパのつもりなのだろう。でも私は少年から投げ掛けられた無神経な一言を不快に感じた。
「からかわないでください」
気味悪がられこそすれ、褒められたことなど無いこの三白眼。真っ黒な長い髪とこの眼の所為で、幼い頃からホラー映画の主人公の渾名で揶揄されてきた。この眼はまさに、剥き出しにされた私の劣等感そのものであり、私にとっては忌まわしいだけの存在でしかない。そして少年の言葉は、まるでその眼球に無造作に触れてくるざらついた指先だった。
「戯れではないぞ」
足早に立ち去ろうとする私を、意外なほどの圧力を持つ返事が呼び止めた。
「あのう、いいかげんに…」
失礼な言動を詰ろうと振り返り、改めて少年を眺めた瞬間、私の視線は絡め獲られ、言葉を失ってしまった。女性と見紛う端正な顔立ち。外見にそぐわない年経た雰囲気。聞く者を魅了せずには置かない声。真意を読み取らせない深淵のような瞳。まさに神か、それとも悪魔か、私は一瞬にして少年に魅せられてしまった。ここは西日暮里駅前。冷静に考えれば、そんなところに神は宿らないに違いない。だけど私には関係なかった。少年が悪魔だろうと神だろうと。この刹那に私が抱いたのは恋愛感情と言うよりは奴隷の忠誠心、いや、狂信者の信仰心に近い感情だった。
「お前を我輩の女にしてやろうか?」
その日から少年との奇妙な関係が始まった。
その少年の女になったと言っても、対等な立場からは程遠い。私は少年の連絡先を教えてもらえず、一方的に呼び出され、何かしらの命令を受けるだけだった。それでも私は満たされていた。
ある時は、男物の分厚いコートを着込み、南京袋を頭に被り、その上から帽子を被らされた。ビデオ屋に並んだ古い映画のパッケージか何かで見覚えがある格好だ。その姿で、西日暮里駅を歩く水色の髪の少女に何故か体当たりさせられた。
また、その直後に白いワンピースを着させられ、同じ少女を自宅のお寺で襲うように命ぜられた。私は生まれつき舌がとても長く伸びる。その舌で彼女を驚かしたところを間一髪で少年が助けに入った。私はすぐにその場から逃げ去ったので、その後どうなったかは知らない。
どちらも少年からはただの悪戯だと説明されたが、彼女が何者なのかは教えてもらえなかった。私にとって、少年にとって、敵なのか、味方なのかも分からない。でも私には少年に真実を問いただす勇気など無かった。戦略的(ストラテジック)に判断停止(エポケー)したとでも言えば少しは聞こえが良いかも知れない。でも実際は少年に捨てられるのが恐かっただけだ。
翌日、私は精一杯お洒落をして、少年と腕を組み駅前を歩いた。それが私が得られた唯一の、そして十二分な御褒美だった。こちらを向いた少年の瞳の深淵を覗くと、かつては忌わしい存在でしかなかった私の瞳がそこに映りこんでいた。
それからしばらく、少年から連絡の無い日々が続いた。久しぶりに少年から呼び出された時、自分でも愚かしく思うほどの安堵感が全身を包んだ。飼い主を迎える仔犬のように、私は少年の元へ急いだ。白い学生服を着た少年は、私にこんな申し出をしてきた。
「とある病院に潜入してくれまいか」
私は唯々諾々として命に服すことにした。その病院が精神病院であろうと、院長やスタッフが怪しげであろうと問題ではない。少年が望んでいるという理由だけで私には充分だ。
「ちょびっと私用でチベット修行ね」
入口で少年と別れるとき、病院の外観に掛けたそんな冗談を言った。すると少年はいつに無く真剣な調子で私にこう告げた。
「我輩が必ず迎えに行くであろう」
私は自分の瞳に彼の面影を焼き付けた。そして適当な症状をでっち上げ、その病院へ入院した。
あれからどれだけの日々を過ごしたろう。当たり前だが病院での生活は陰々滅々たるものだった。
白い箱のような病室。昼となく夜となく常に狂人の声で喧しい廊下。「ブウウーーーンン…」と鳴る気味の悪いボンボン時計。現世とは違う次元を生きる患者たち。
中でも全身を緑色の粘液で覆われたぬめり川という患者は超が付くほど気持ち悪かった。初めて会った時、キョロキョロと定まらぬ視線で熱心に私にアピールしてきたが、あれは何の積もりだったのだろうか。あれ以来、ぬめり川を避けているので今以って謎である。
このような環境に長いこと身を置けば、誰であろうと狂気が心に宿ることだろう。少年との約束という一縷の望みが、辛うじて私に正気を保たせている。でも、その限界も近そうだ。
毎日連れ出されるこの解放治療場だが、狂気の淵へと追い込んでゆく実験場としか思えない。向こうで畝を耕している鍬が、いつか凶器になって私たちを襲うのではないかと妄想してしまう。今、目の前を通り過ぎた看護婦があの水色の髪の少女に見える。隣の患者が吹く笛の音を聞いていると、私の眼窩から眼球が飛び出て歩き出しそうな錯覚を覚える。
私は万が一にも眼球が飛び出さないように、そっと瞼を閉じた。必ず迎えに行く、と言ってくれた少年の面影がそこには焼きついていた。
「奇麗な眼をしておるな」
かつて少年が誉めてくれた瞳に、このキチ○イ地獄の光景はこれ以上映すまい。
そして私は眼を瞑り、少年が迎えに現れるのを今日も待っているのである。
SaltyDogの犬小屋
オフロード・バイク、セロー・SEROWでの林道キャンプ・ツーリングをレポート